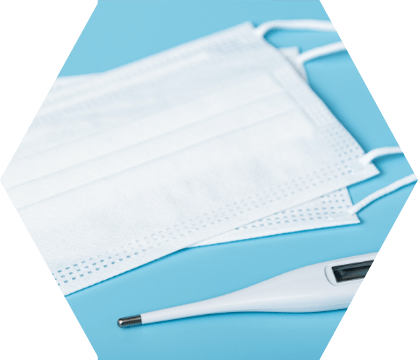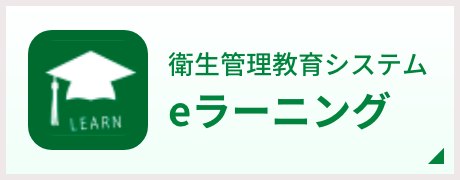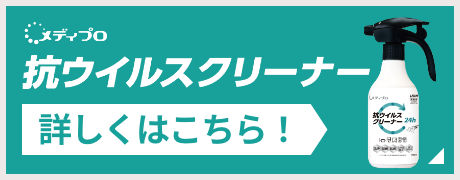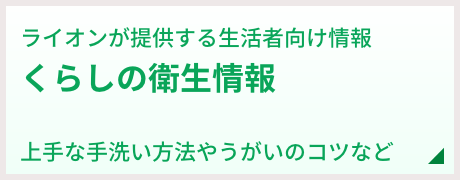食中毒の原因について

食中毒とは、食品が原因となった下痢や腹痛、発熱や吐き気などの胃腸炎、神経障害等の中毒症の総称になります。厚生労働省による食中毒統計では原因となった物質によって、細菌が原因物質となる食中毒、ウイルスが原因物質となる食中毒、寄生虫が原因となる食中毒、化学物質が原因となる食中毒、毒キノコ、フグ毒、かび毒など植物由来や動物由来の自然毒が原因となる食中毒、その他の食中毒、原因不明な食中毒に分類されます。
このうち細菌性食中毒は、発症機構により感染型と毒素型があります。感染型食中毒とは、食品中に増殖した原因菌(サルモネラ属菌、リステリア・モノサイトゲネス、腸炎ビブリオ、エルシニア菌等)を食品とともに摂取した後、原因菌が腸管内でさらに増殖して発症する食中毒になります。毒素型食中毒とは、食品中で原因菌が増殖し産生された毒素の摂取によって引き起こされる食中毒のことで、黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌、ウエルシュ菌等が原因菌となります。ウイルス性食中毒は、平成15年8月の食品衛生法施行規則の改正により、それまで「小型球形ウイルス」と分類されていたものが「ノロウイルス」に変更され、平成16年の食中毒統計から集計されるようになりました。
食中毒の原因解説一覧
ハイジーンメンバー募集中
便利なコンテンツや過去のハイジーンたよりがダウンロード出来る、ハイジーンメンバーを募集中です。
登録料、年会費等は無料です。
ライオンハイジーンメンバー限定
コンテンツのご紹介
-
 ハイジーンたより バックナンバー 衛生情報をわかりやすく解説した過去のハイジーンたよりがダウンロードいただけます。
ハイジーンたより バックナンバー 衛生情報をわかりやすく解説した過去のハイジーンたよりがダウンロードいただけます。 -
 動画コンテンツ 現場実践に使える洗浄方法や知っておきたい衛生知識が学べる動画をご覧いただけます。
動画コンテンツ 現場実践に使える洗浄方法や知っておきたい衛生知識が学べる動画をご覧いただけます。 -
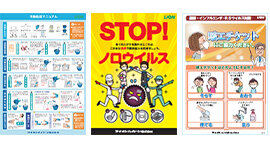 ポスター 従業員の方の意識付けにお役立ていただけるポスター素材をダウンロードいただけます。
ポスター 従業員の方の意識付けにお役立ていただけるポスター素材をダウンロードいただけます。